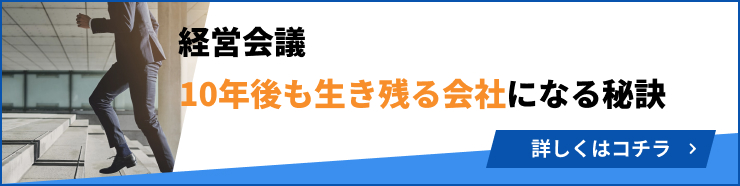経営管理
超簡単!変動費と固定費の分け方【もう固変分解に悩まない】

変動費と固定費の分け方がわからない人
「会社の数字を分析したいのですが、変動費と固定費の分け方がわかりません。簡単でわかりやすい固変分解の方法があれば教えてください。」
こういったお悩みに答えます。
本記事のゴール
3分程で読み終わります。読み終えた後には、変動費と固定費の簡単な分け方がわかり、もう固変分解に悩まなくなるはずです。
こんにちは。近藤税理士事務所の近藤です。
私は、税理士事務所・一般事業会社・企業再生コンサルティング会社勤務を経て独立した少し変わった経歴を持つ税理士です。
税理士業界から一度離れ、倒産危機に陥る会社をたくさん見てきたからこそ、「数字の重要性」を再認識することができました。
その貴重な経験のなかで得た「気付き」や「ノウハウ」をブログに綴って情報発信しています。
「経営を数字という言葉で語れるようになること」
そうすれば、あなたの会社は必ず変われます。
変動費と固定費の分け方(固変分解の方法)

変動費と固定費の分け方、いわゆる固変分解の方法は、大きく分けて2つあります。
ひとつは、勘定科目法による固変分解
その名のとおり、勘定科目で分ける方法です。考え方はいたってシンプルです。
もうひとつは、最小二乗法による固変分解
詳細は割愛しますが、数学的に計算する方法です。Excelを使えば計算自体は難しくはありません。
ここでは、一般的で理解しやすい「勘定科目法による固変分解」の方法について説明をしていきます。
簡単に固変分解するためには、とにかく「シンプルに考える」ことです。
例えば、あなたの会社の損益計算書の費用科目が20個あったとしたら、そのうち変動費となる費用科目は1~3個くらいだと思います。
だったら、費用科目の20個すべてを変動費と固定費に振り分けるのではなく、数の少ない変動費だけをしっかり見極めて、残りはすべて固定費と考えれば良いだけのこと。
ねっ、簡単でしょ?
変動費
変動費とは「販売数量に比例して生じる費用」をいいます。
材料費や仕入原価、外注加工費や販売手数料などが変動費にあたります。
ちなみに、変動費のことを「売上高に比例して生じる費用」と理解されている人がいますが、大きな間違いです。変動費は、売上高に比例しません!
固変分解で行き詰っている人は、こんな感じで悩んでいます。
- 給料は固定費でも、残業代やパート・アルバイト代は忙しいときに支払うから変動費になるのではないか…?
- 電気代のうち基本料は固定費で、毎月の使用量に応じて支払う分は変動費になるのではないか…? など
こんなことを考えていたら、日が暮れてしまいます…
繰り返しになりますが、変動費とは「販売数量に比例して生じる費用」です。
つまり、その費用が「販売数量に比例するのか?しないのか?」だけにフォーカスして固変分解すれば良いのです。
先ほどの例でいうなら、残業代やパート・アルバイト代は販売数量に比例しませんから、もちろん変動費ではなく固定費です。
真夏にエアコンをガンガンに使ったら、電気代は増えますが販売数量には全く関係ありません。これも固定費です。
このように固変分解していけば、あなたの会社の損益計算書で変動費になる勘定科目はおのずと限定されてくると思います。
固定費
固定費とは、「販売数量に関係なく生じる費用」をいいます。
つまり、変動費以外の費用はすべて固定費としてください。それだけです。
固変分解にあたっての注意点

固変分解にあたっての注意点は、大きく2つです。
- 注意点①:変動費を間違えないこと
- 注意点②:あまり細かく考え過ぎないこと
注意点①:変動費を間違えないこと
経営分析をするうえで、固変分解はとても重要です。
だから、変動費となる勘定科目を間違えないように注意してください。変動費を間違えると正しく経営分析ができませんので。
慎重に変動費を見極めましょう。
注意点②:あまり細かく考え過ぎないこと
経営分析の目的は、会社の数字を大局的な視点で把握することにあります。
だから、固変分解をあまり細かく考え過ぎて思考停止しないようにしてください。1円単位の細かい数字を合わせることが目的ではありませんから。
固変分解は、そんなに時間をかけるものではありません。
何のために固変分解をするのか?

これまで固変分解の方法や注意点を見てきましたが、いったい何のために固変分解をする必要があるのでしょうか…?
それは、ズバリ「損益分岐点」を計算するためです!
損益分岐点は、「会社の健康状態」を測る重要な経営指標です。継続して儲かっている会社では、「損益分岐点」の考え方をうまく経営管理に活かしています。
つまり、この損益分岐点の考え方をしっかりと理解できれば、あなたの経営に対する姿勢が大きく変わることになると思います。
損益分岐点について詳しく知りたい方は、こちらの記事がおススメです。
まとめ
「勘定科目法による固変分解」の方法について書いてきました。
固変分解は、とにかくシンプルに考えること。
変動費は「販売数量に比例して生じる費用」です。費用科目のうち、変動費となるのは1~3個くらいだと思います。その変動費だけを見極めることができたら、残りはすべて固定費。
たったこれだけです。
ぜび実践してみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。よろしければ、下記の当事務所サービスページもご確認いただけると嬉しいです。